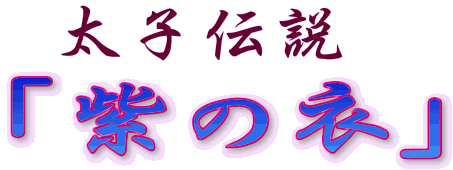
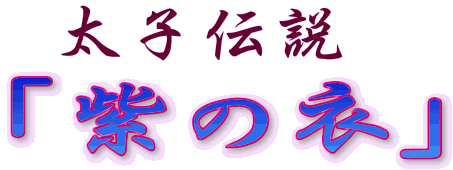
|
1.序 |
| 2.道ばたにて 馬を下り、近づいてみると、そこには人がたおれていました。ゆきだおれたのか、やせおとろえてぐったりとしています。 「どうしたのですか?」 声をかけても、答えることもできません。ただ、切れ長の目をいっぱいに見ひらき、太子を見つめました。太子は何か胸をつかれるような気がしました。その目はするどく、なにか不思議な光があったからです。 そまつな身なりでしたが、その体からはとても良い香りがただよっていました。 |
| 3.寒空の下 太子は哀れに思い、持っていた弁当と飲み物を与えました。そして、着ていた紫の衣をぬぎ、寒さにふるえるその体に着せかけようとしました。 「太子様、それはみかど様にいただいた、大切なお着物です。」 供の者がとめようとしましたが、かまわず歩み寄りました。 「よいのです」 太子はやさしい笑みをうかべ、そっと着せかけてやりました。 「どうか安らかにお休みなさい」 と声をかけると、心を残しながら斑鳩の宮へと帰って行きました。 |
斑鳩の宮に帰ってからも、どうしても気になってなりません。 「だれか、もう一度、あの方の様子をみてきてくれぬか」 と使いを出しました。 しかし、その方はすでになくなっていたのです。 悲しく思われた太子は、その場所に墓をたて、手厚く葬られました。 |
| 4.花のたより 厳しい寒さはやわらぎ、花の便りも聞かれるようになりました。しかし、何日たっても、あの目の光を見たときの不思議な思いがきえません。 「あの方は、とても尊い方のような気がしてならない」 あれこれと考えた末に、ふたたび使いを出して調べさせました。 不思議なことにお墓にはその方の姿はなく、ていねいにたたまれた、あの紫の衣だけが残っていたというのです。 |
| 5.紫の衣(終曲) 太子は、持ち帰られたその衣をじっと見つめました。 「あの尊い方は、世のこと人々のことをたくされたのかもしれない。わたしはこれまで以上に、はげまねばならない」 そんな気持ちが、体の中からあふれてくるのでした。 太子は紫の衣を身にまとい、外に出ました。中庭の梅の小枝はかわいいつぼみをつけ、もう、春を待つばかりです。信貴の山から吹き下ろす風が、斑鳩の里を静かに吹き抜けていきました。 |
| (2005年3月 文 : 西崎悠山) |